お知らせ
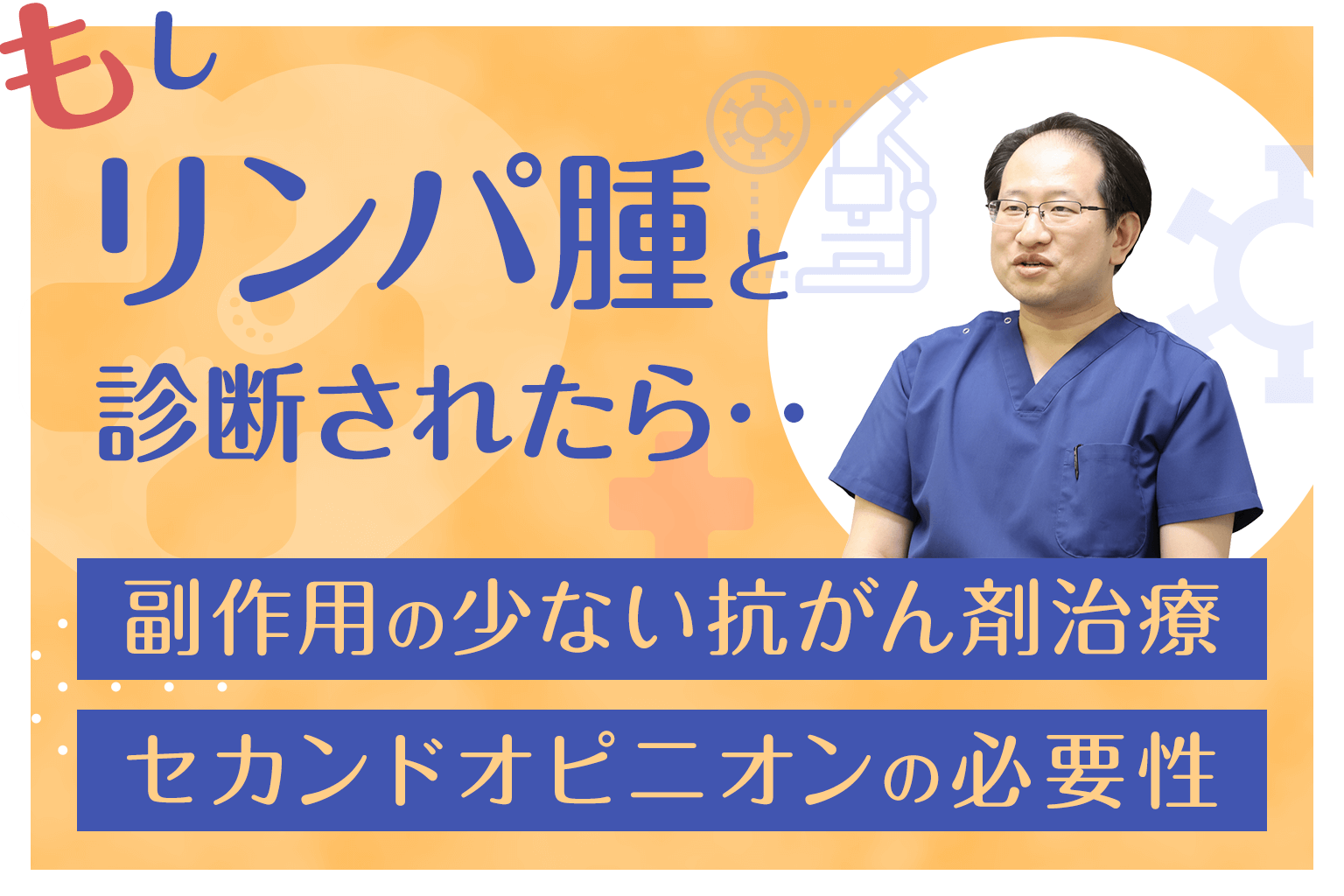
2025.10.08
もしリンパ腫と診断されたら―副作用の少ない抗がん剤治療とセカンドオピニオンの必要性
愛するペットが「リンパ腫」と診断されたとき。飼い主さんの不安はとても大きいものです。
ペットのためにどんな治療をするべきか、どの動物病院にかかるべきか迷われる方も多いでしょう。
私は大学病院時代から15年以上にわたるリンパ腫診療の積み重ねを通じて、専門的な二次診療施設と同レベルの医療検査・治療を提供しつつ、「病気と付き合いながらその子らしい生活を送れること」が重要であると考えています。
今回は、愛犬・愛猫のリンパ腫でお悩みの方やセカンドオピニオンを検討されている方へ、治療方針や動物病院の選び方についてお話しします。
体の「できもの」「しこり」に要注意。リンパ腫の症状と生存率について
リンパ腫の種類と発見のきっかけ
リンパ腫とはリンパ系の細胞(リンパ球)のがんで、「多中心型」「消化器型」「皮膚型」などに分類されます。
リンパ腫の中で最も多いのは多中心型リンパ腫で、体の表面のリンパ節があちこち腫れてきます。初期は症状が少なく、ペットの体を触ったときに「顎の下にコロっとした大きいできものがある」「肩口にしこりがある」といった飼い主さんの気づきがきっかけで見つかること大半です。
生存率と個体差
ヒトの医療ではリンパ腫は根治可能な病気である一方、獣医療はまだ追いついていない部分があり、一般的な多中心型リンパ腫は、1年生存が約50%、2年生存が約25%と言われます。
ただ生存率には個体差があり、当院では7年間生存を続けているワンちゃんもいます。
ペットの身体を撫でているときに感じる違和感を見逃さず、気になる箇所があれば獣医に診てもらいましょう。
その子のためのオーダーメイドに近い抗がん剤治療の方針を提案
診断のための検査と分類
リンパ腫は遺伝子検査や免疫染色、細胞診などで診断します。リンパ腫に似た腫瘍もあるため、まずは細い針で腫瘍の細胞を取って検査する必要があるのです(その子の状態によってはリンパ節ごと切除することもあります)。
リンパ腫にはT細胞とB細胞があり、どちら由来かで投与するべき抗がん剤が変わりますので、フローサイトメトリー法(細胞の表面に抗体をつけて性質を調べる検査)や、レセプターに基づく遺伝子検査を組み合わせ、T細胞由来かB細胞由来かをはっきりさせます。
最適な抗がん剤選択の重要性
また、リンパ節の腫れだけではなく、消化管や脾臓にまでがんが侵食していることもありますから、リンパ腫の種類や広がりの範囲まで把握して、最も効果的でかつ体への負担が少ない抗がん剤を選択します。この選択を誤ると状態が悪化したり、副作用が強く出て生活の質が下がったりということになるため精密な診断が必要なのです。
検査精度の向上と個別化治療
近年は、腫瘍細胞を検査機関へ送り、複数の抗がん剤に対する感受性を調べることもできるようになってきました。
従来は「このタイプならこの薬が効きやすい」と統計に基づく一般論が中心でしたが、今は「この子にはこれとこれが効きやすいから、この組み合わせでいこう」といったオーダーメイドに近い提案が可能になっています。当院では多数の抗がん剤を揃え、検査結果に応じた治療設計ができる体制を整えています。これにより、リンパ腫と診断された子でも、より長く安定して過ごせるケースが確実に増えていると実感しています。
大切なのは“その子らしく生きること” ― 私がQOLを重視する理由
延命よりも生活の質を大切に
抗がん剤に対しては、「食欲がなくなる」「嘔吐する」「毛が抜ける」といったイメージが強いですよね。もし病気の根治が現実的であれば、「厳しくてもやろう」と私も背中を押せます。しかし犬・猫のリンパ腫では、現状“延命”の意味合いが大きいのが事実です。だからこそ私は、その間をどう生きるかをとても大切にしています。
副作用を抑えるための工夫
私が考える「ワンちゃん・ネコちゃんらしい」生活は、普通に散歩ができて、ある程度ごはんをちゃんと食べられることです。延命できたとしても、その間ずっと飲まず食わずでぐったりしていたら、幸せな暮らしとは言えないと思うのです。
ですから、副作用をなるべく出さない治療計画がとても重要です。そのためには、病気の広がり(ステージ)を厳密に評価し、どの薬を、どのタイミングで使えば副作用が起きづらいかを考え抜く必要があります。腫れているから針を刺して「リンパ腫だね、じゃあ標準薬で治療しよう」という手荒な進め方では、重篤な副作用が起き得ます。広がり方に合わせて最適な薬と順序を選ぶ――ここを私たちは一番大切にしています。
治療しないという選択も尊重
一方で、無理に治療をしない勇気も必要だと私は考えます。治療が難しいと思われるほど全身状態が悪いときには、私は抗がん剤を強く勧めません。治療を行っても、その子につらい思いをさせるだけになってしまう可能性が高いからです。血液検査など客観的なデータに基づいて「耐えられる」と判断できる状況なら提案します。いずれにしても“その子”にとってどうするのがベストかを軸として、治療方針について飼い主さんと相談するようにしています。
経験から学んだ治療方針
正直に申し上げますと、これまでリンパ腫治療を続ける中で、苦い経験も少なくありませんでした。
私の経験がまだ浅かった頃、セオリー通りの抗がん剤治療を行った結果、飼い主様から「長生きしたけれど副作用で辛そうだった。もう抗がん剤はやらない」と言われたことがありました。そのとき、たとえ治療としては成功にみえても、飼い主さんや動物たちに大変な思いをさせてしまう治療は勧めるべきでないと感じたのです。
それらの経験が今の価値観と治療設計に生きています。QOLを重視するようになってからは、「抗がん剤治療をやってよかった」というお声を本当に多くいただくようになりました。
次の子を迎えたときにも、また当院を選んでくださる方が多いのは、きっとこの治療方針に納得感があるからだと思っています。
セカンドオピニオンの意義――迷ったら、納得できる先生を探してください
セカンドオピニオンを前向きに捉える
私は、セカンドオピニオンは自然な選択だと思っています。
動物医療はある意味サービス業の側面があり、すべての病気が得意な先生はいません。飼い主様と価値観が合わないこともあるでしょう。
今はネットで情報がたくさん手に入るので、飼い主様も事前に勉強してくる方が多いです。でも、ネットで見た情報が本当に正しいのか、うちの子に当てはまるのかを判断するのは難しいですよね。
もしかかりつけの動物病院があったとしても、他の獣医師の意見もききたいと感じたら、いろいろ回っていただいて相談をして、一番納得感のある先生のもとで治療されるのが、飼い主さんにとっても後悔がないのではと思います。
飼い主様と価値観を共有する
私は時間の許す限り飼い主様からお話を伺い、客観的データに基づく選択肢をご提示し、選択肢のメリット・デメリットをわかりやすくお話しして、飼い主様のご希望に近いアプローチを一緒に探すことを大切にしています。
セカンドオピニオンで当院に来られた飼い主様から「先生がちゃんと話を聞いてくれないと感じて不安になった」と理由を伺うことがあります。
規模の大きな病院などは獣医師も多忙な環境ですから、一人ひとりの相談に割く時間も限られています。その子をどれだけ理解して治療してくれているのか不安になりやすいのです。
費用面の現実と柔軟な提案
費用の面も正直にお話しします。こういう治療があって、これくらい費用がかかる。この治療ならここまで、といった現実的なラインも一緒に検討します。
抗がん剤は1回数万円する薬もあり、決して安価な治療ではありません。継続投与の方が効果は望めるのですが、毎週の投与が難しい場合でも「では月に1回投与にしましょう」と提案することもあります。「できる限りの治療はしてあげることができた」と飼い主さんも納得することが後悔がなくなるからです。
もちろん、飼い主様の考えで治療を途中でやめるという選択も有りだと考えます。
私は獣医師として事実とアドバイスをお伝えしますが、最終的に決めるのは飼い主さんだと思っているからです。
飼い主様と“一緒に考える”治療方針
診断内容を共有する工夫
愛犬・愛猫の治療が飼い主様の後悔につながらないように、コミュニケーションを何より大切にしています。
初診後は診察・診断内容をメールでまとめてお送りするようにしています。リンパ腫や心臓病など衝撃の大きい診断結果の場合、飼い主様も動揺してその場で言われたすべてを覚えておくのは難しいものです。
診断内容や治療方針などをお家で見返せるようにすると、飼い主様もご家族と相談しながら落ち着いて治療について考えられますし、病院としてお伝えしたことが正しく伝わり、誤解やトラブルも防げます。
加えてメールアドレスも公開しておりますので、メールでいただいた相談には、朝でも夜でも夜中でも体力の許す限りすぐ返信しています。飼い主様の不安な時間を少しでも短くしたいので、常にスマホを手元に置いて、すぐ対応できるようにしています。
飼い主様の意思を尊重した決定
治療方針を決めるときは、費用や通院頻度まで含めて、何を望んでいるのか、何が不安なのかを真剣に向き合って伺います。専門家として正しい情報をわかりやすくお伝えし、判断材料にしていただいたうえで、最終的な決定は飼い主さんに委ねます。私は、その決定を全力で支える立場にいたいと思っています。
専門性と安心感の両立
迷ったら、すぐにご連絡ください。電話でもメールでも大丈夫です。
私は「専門性」と「安心感」の両方を、同じだけ大切にしています。その子らしく暮らす時間を一緒に守るために、できることをひとつずつ積み重ねていきます。どうかひとりで抱え込まず、いつでも相談してください。
ご相談・ご予約は 北央どうぶつ病院(札幌市厚別区)
TEL:011-893-1010






